「海外に行きたいけど、英語が話せないから…」
「外国で言葉が通じなかったらどうしよう…」
そんな不安を抱えていませんか?
安心してください! 英語がペラペラじゃなくても、海外旅行は十分楽しめます。むしろ、言葉が通じない中で旅をすることで得られる体験は、かけがえのない思い出になることも。

私自身、英語が得意ではない時期もありました。それでも、話せない状況のときから旅を始め、これまで30カ国以上を旅してきました。最初は不安でしたが、準備と工夫次第で言葉の壁はかなり低くなります。
観光庁の調査によると、「語学力の不安」を理由に海外旅行をためらう日本人は年々減少しているのだとか。それは、スマホの翻訳アプリなど便利なツールが増えたことも大きな理由です。
この記事では、英語が話せなくても海外旅行を存分に楽しむための方法をご紹介します! 出発前の準備から現地での対応まで、実践的なアドバイスを紹介するので、お役に立てると幸いです。
出発前の準備 |言葉の不安を減らす事前対策

旅の成功は準備で決まります。
特に言葉に不安がある場合は、出発前にできることがたくさんありますよ!
基本的な挨拶と単語を覚えよう
現地の言葉で「ありがとう」「すみません」「こんにちは」などの基本的な挨拶ができるだけで、地元の人との距離がぐっと縮まります。発音が完璧でなくても、チャレンジする姿勢が大切です。
Thank youはもう大丈夫ですよね?
それでは他の国の言葉をみてみましょう。
たとえば:
旅行会話集・ポケット辞書を活用しよう
スマホが使えない場合に備えて、小さな旅行会話集やポケット辞書を持っていくと安心です。特に、写真やイラスト入りの「指さし会話帳」はおすすめです!

文字が読めなくても、絵を指さすだけで意思疎通ができます。便利!
便利な翻訳アプリをダウンロードしておこう
出発前に翻訳アプリをダウンロードしておきましょう。特にオフライン機能があるアプリがおすすめです。
おすすめアプリ:
- Google翻訳:カメラ翻訳やオフライン機能が使える
- DeepL:精度の高い翻訳が特徴
- Microsoft翻訳:複数人での会話翻訳機能があり便利
宿泊先や観光地の情報をメモしておこう
行きたい場所や宿泊先の名前・住所を現地語と日本語の両方でメモしておくと便利です。
特にタクシーの運転手さんに見せる用のメモは必須アイテムです。スマホのメモアプリに保存するだけでなく、紙に印刷しておくと、電池切れの時も安心です。

一度、空港から電車に乗って街についてから、WIFIが全く拾えないことがありました。(トルコ・イスタンブールにて)そのときに印刷しておいたホテルの情報とマップがあったおかげで、現地の方に助けられました!
最新翻訳ツール活用術

現代の旅行者にとって、テクノロジーは最強の味方です。上手に活用して、言葉の壁を乗り越えましょう!
AIリアルタイム翻訳アプリを使いこなそう
Google翻訳のような翻訳アプリは、会話モードを使えば、お互いの言葉をリアルタイムで翻訳できます。レストランやお店での会話に便利です。
使い方のコツ:
カメラ翻訳機能で看板やメニューを読もう
Google翻訳などのカメラ機能を使えば、看板やメニューをかざすだけで翻訳できます。レストランでのメニュー選びや、道案内の看板を理解するのに役立ちます。
オフラインでも使えるように、現地の言語パックを事前にダウンロードしておきましょう。Wi-Fiがない場所でも安心です。
タブレット・スマホを活用した効果的なコミュニケーション
言いたいことが複雑な場合は、翻訳アプリで文章を作って画面を見せるだけでもOK。
また、写真を見せたり、絵を描いたりするのも効果的です。例えば、欲しい商品の写真を見せれば、どこで買えるか教えてもらいやすくなります。
非言語コミュニケーションの達人になる
言葉だけがコミュニケーションではありません。体の動きや表情も大切な伝達手段です。
世界共通のジェスチャーを活用しよう
多くのジェスチャーは世界共通で理解されます。
たとえば:
- 食べる動作(口に手を運ぶ)
- 飲む動作(コップを持ち上げる仕草)
- 支払いを求める(空中でペンを持つ動き)
- 写真を撮りたい(カメラのシャッターを押す真似)
ただし、国によって意味が違うジェスチャーもあるので注意が必要です。親指と人差し指で輪を作る「OK」のジェスチャーは、一部の国では失礼な意味になります。
渡航先の文化やタブーとなる事項を事前にチェックしておきましょう!
表情や体の動きで気持ちを伝えよう
笑顔は世界共通の「友好」のサインです。困っている時は、悲しい表情を作ったり、肩をすくめたりすれば、多くの場合助けてもらえます。
「わからない」という時は、首を傾げる動作が効果的です。うなずきや首振りも、多くの文化で「はい」「いいえ」の意味で通じます(ただし、インドやブルガリアなど一部の国では逆の意味になる場合もあります)。
指さし会話帳を作って活用しよう
自分だけの「指さし会話帳」を作るのもおすすめです。スマホに、よく使いそうな絵や写真を集めておき、会話の時に見せるだけでコミュニケーションができます。
たとえば:
- トイレの絵
- 水のボトル
- バスや電車の写真
- 数字のリスト(値段交渉用)
- 地図のスクリーンショット
言語フレンドリーな国・地域選び
旅行先によって、言語の壁の高さは大きく変わります。初めての海外なら、言語サポートが充実している国から始めるのがおすすめです!
日本語対応が進んでいる国・都市
近年、日本人観光客向けに日本語対応を進めている国や都市が増えています。
日本語対応が充実している地域:
英語以外の言語圏でも旅行しやすい地域
意外かもしれませんが、英語圏以外でも旅行しやすい国はたくさんあります。
参考記事:
旅行形態を工夫する
個人旅行に不安がある場合は、以下のような旅行形態を選ぶと安心です。
実践編:具体的なシチュエーション別対応策
実際の旅行中によく遭遇する場面での対処法をご紹介します。
空港・入国審査での乗り切り方

入国審査では基本的な質問(滞在目的、滞在期間、滞在先)しか聞かれません。以下の簡単な英語フレーズを覚えておくと便利です。
「I’m here for tourism」(観光目的です)
「I’ll stay for [数字] days」(○日間滞在します)
「I’m staying at [ホテル名]」(○○ホテルに泊まります)
こちらの記事も参考にしてくださいね。
事前に入国カードの記入例を調べておくと安心です。また、ホテルの予約確認書を印刷して見せられるようにしておきましょう。
ホテルでのチェックイン・アウト
ほとんどのホテルでは、予約番号とパスポートを見せるだけでチェックインできます。事前に予約確認メールをプリントアウトしておくと便利です。
チェックアウト時は「Check out, please」と言って鍵を返すだけでOKです。追加の支払いがある場合は、電卓や紙に書いた数字で金額を確認しましょう。
参考記事:
https://travelota.jp/hotel-check-in-english-phrases/
レストランでの注文方法
メニューに写真がある店を選ぶと安心です。写真がない場合は:
- 他のお客さんの料理を指さして「Same one, please」
- Google翻訳のカメラ機能でメニューを翻訳
- 定番料理の名前だけ覚えておく(例:パスタ、ピザ、パッドタイなど)
アレルギーがある場合は、該当する食材の写真に×印をつけたカードを用意しておくと便利です。
参考記事:
交通機関の利用方法
タクシーでは、行き先の名前や住所を書いたメモを見せるのが最も確実です。また、地図アプリで目的地を表示して見せるのも効果的です。
電車やバスでは、路線図を見ながら目的地の駅名を指さすだけでチケットを買えることが多いです。また、駅名や停留所名は車内アナウンスをよく聞くか、スマホの位置情報で確認しましょう。
トラブル時の対応
道に迷った時は、地図アプリを見せながら「Where is this?」と聞くだけでOK。最悪の場合は、タクシーを拾ってホテル名が書かれたカードを見せれば、ホテルに戻れます。
病気になった場合は、体調不良を表す絵や症状を表す写真(頭痛、腹痛など)を見せると薬局でも適切な薬を勧めてもらえます。ただし、深刻な症状の場合は、ホテルのフロントに助けを求めましょう。
参考記事:
お土産購入時の値段交渉術
値札がない店では値段交渉が一般的です。スマホの電卓アプリを取り出して希望価格を打ち込むだけで交渉できます。最初は提示価格の半額くらいから始めるのが基本です。
参考記事:
言葉の壁を恐れずに踏み出す一歩
言葉が通じなくても、海外旅行は十分楽しめます。むしろ、言葉の壁があるからこそ生まれる出会いやエピソードが、かけがえのない思い出になることもあります。
完璧な準備よりも「なんとかなる」という気持ちが大切です。困った時は、笑顔で助けを求めれば、世界中どこでも親切な人は必ずいます。
言葉の心配より、行動する勇気を持つことが大切です。一歩を踏み出せば、新しい世界があなたを待っています。言葉の壁を超えた先には、何物にも代えがたい旅の体験が広がっているはずです。

トルコは、とても親日国だったこともあり、かなり興味深い経験ができました。ハンサムなトルコ人にカーペットを売りつけられそうになったことも、今では良い思い出です。(安全面には注意しましょう)
次の旅行計画を立てる際は、この記事で紹介した準備と心構えを参考に、ぜひ挑戦してみてください。言葉ができなくても、素晴らしい旅ができることを、身をもって実感できるはず!
著者プロフィール:
メディア一覧:


















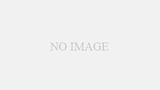


コメント